
砂利道の向こうに
宮城県石巻駅から北に向かい、北上川を左に見ながら北東に進む。新北上大橋を右に入ったところに雄勝町がある。
雄勝の景色は10年前の東日本大震災で大きく変わった。そして、今も変わり続けている。高い堤防が伸び続ける中、寄せては返す波の形をどこに行けば確認できるだろうか。
そんなことを考えながら、今回の目的地「エンドーすずり館」の看板を探していた。同じところを行ったり来たりしているのを見かねたのだろう。堤防工事のトラックに乗った人が、窓から顔を出して「どこに行きたいの?」と声をかけてきた。場所を告げると、「一本奥の道のさ、砂利道の向こうにあるよ」と教えてくれた。
やっと見つけた「エンドーすずり館」の扉を開けると、敷き詰めるように置かれた硯に目を奪われた。直売所の横に作業場がつながっているらしい。蛇口から水の流れる音が聞こえていた。作業場に向かって「こんにちは」と言うと、奥から「はぁーい」という明るい声が聞こえて、硯職人の遠藤弘行さんが出てきた。

石を見ること
硯には、雄勝の玄昌石が適している。採ってきた原石を見て、硯の形を決めて加工していく。遠藤さんの作品には、石本来の色や形を残したものや、それを生かして絵を描き彫刻を施したものがある。中には貝の化石が埋まっている硯もあって、自然の息遣いを感じることができる。
作業場で、墨をする「陸」と水をためる「海」をつくる工程を見せてもらった。ノミの柄を肩の下の部分にあて、体重を乗せるように石を彫っていく。ゴリゴリという音が、石の硬さを物語る。ノミの柄があたる部分にはたこができるという。
石の粉が飛んで、少しずつ陸と海がはっきりしてくる。仕上げにノミで削った跡を砥石で平らにし、紙やすりで磨く。石が硯になっていく過程すべてが職人の感覚と技によって行われる。
遠藤さんは2011年の津波で、自宅と店と作業場を兼ねた家を流された。がれきの中から遠藤さんの父、盛行さんのつくった硯が見つかったことが、遠藤さんをもう一度硯づくりに向かわせた。ノミなどの道具を引退した職人から譲り受け、プレハブの小屋を建てて制作を再開したのは震災から3ヶ月後の6月12日だった。



ネズミのはしる山
「ここにネズミがはしってる」。遠藤さんが、雄勝の玄昌石の分布図を指しながら言った言葉が面白かった。玄昌石には黒石、白石、ネズミ石があって、この3種類の石脈が同地域に通るのは世界でも類を見ない。そんな宝の山で、遠藤さんの家は代々採石業を営んできた。
3代目の盛行さんが採石業をしながら独学で硯づくりを始め、遠藤さんも同じように、採石から硯づくりまでを一人で行っている。学校を出てから神奈川で働いていた遠藤さんが、地元に戻って盛行さんに弟子入りしたのは24歳の時。
それから10年ほどの修業を経て、雄勝湾沿いに「エンドーすずり館」を開店した。盛行さんは直売という形にこだわり、「せっかくここまで来てくれたから」と最高品質の硯を手に取りやすい値段で販売していたという。遠藤さんの作品も1000円台からという価格設定になっている。
出来上がった硯で墨をすらせてもらうと、吸いつくような感覚があって少しの抵抗もない。これを「墨おりが良い」というらしい。濃度も量も、使い手の思う通りにできる。

使い手との対話
直売所のレジの横にいくつかのファイルが立てかけてあった。そこには遠藤さんの硯を愛用している書家や墨絵画家からの手紙が丁寧に収められている。使い心地や硯への評価が記されている部分は暗記しているようで、遠藤さんがうれしそうに紹介してくれた。
直売所でネズミの硯を購入した。茶色い石の模様も勢いのある形も、見ていて飽きがこない。硬くて加工しにくいため使われてこなかったネズミ石や白石を、硯の素材として用いたのは盛行さんが最初だといわれる。
それまでスレート用に薄く割れる石が重宝され、それ以外は捨てられていたが、捨てられた中に盛行さんの探していた硯に最適な石が埋もれていたという。誰より石を知る人によって見出された原石と、継承された確かな技術によって生まれた名品がここにある。
取材を終えて帰ろうとすると、遠藤さんが「今度硯を使った感想を教えてください」と言った。その見送り方が職人としての生き方を表している。
協力:エンドーすずり館
〒986-1333
宮城県石巻市雄勝町雄勝船戸神明68
テキスト:平山朋子
取材記者。北海道から沖縄まで、被災地等を中心に取材を行う。方向音痴で道に迷うことが多く、いつも現地の人に助けられている。平日は児童館で子どもたちと遊ぶ。造形活動が好き。
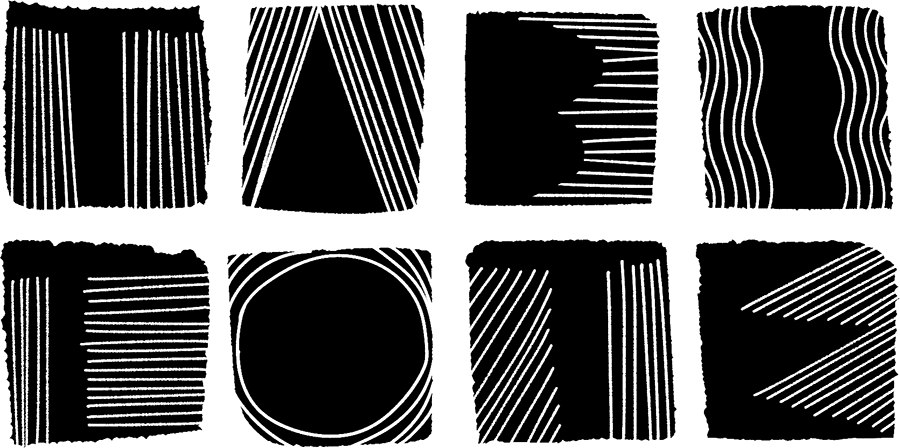






















COMMENTS