
4日目 舩木窯と出雲民藝館
最終日の午前中は布志名・舩木窯にお邪魔した。到着した場所は宍道湖の湖畔。すぐ目の前に素晴らしい湖の景色が広がっていた。かつて焼き物の輸送手段が海上輸送だった頃、この入江が船着場になっていて、製作した焼き物を全国に出荷していたそうだ。
布志名焼の歴史はとても古く、約300年前から続いている。元々は松江藩の御用窯として庇護を受け、お茶道具などを作っていたが、明治時代に御用窯が衰退すると、海外の博覧会に出品したり輸出が盛んになっていった。そして輸出産業が斜陽になる頃、四代目の舩木道忠は民藝運動のメンバーと交流を深め、個人作家としての道を歩むことになる。



舩木窯が島根の他の窯と異なる点は、民藝運動のメンバーと交流し、その影響を受けながらも、作家性を押し出した作品づくりをしているところだ。来待釉など地場の材料を使い、スリップウェアの技法を取り入れた民藝の影響を感じる作品は非常に興味深い。
午後は電車で出雲民藝館を訪ねる。松江駅から山陰本線の西出雲駅まで電車に揺られる。駅からは徒歩10分ほど。他の民藝館と同様に建物がすばらしい。
出雲地方きっての豪農だった山本家の邸宅を一部改修し、そのまま展示館として使っているそうだ。そのため、中央の母屋には、現在も山本家の方々が住んでいるという、すこし変わった民藝館だ。


展示館は本館と西館に分かれていて、両方合わせてもそれほど広くなく、気軽に見てまわれる。展示されている品物には、島根の地域性が見て取れる。午前中に見学した布志名焼はもちろん、石見地方の大甕(おおがめ)がいくつも並び、藍染の大風呂敷や蒲団地が広がる光景は迫力があった。
また、有名なたたら製鉄の道具や、屋外には昔の農民が使用していた農具まで集められていた。他の民藝館と比べても、かなり地域性が色濃い展示でとても楽しめた。
今回は出雲地方を中心に回ったが、同じ島根県でも西側の石見地方に行くと、出雲とはまたぜんぜん違ったものを見ることができるらしい。次の旅では石見を中心に巡ってみたい。
出雲民藝館
島根県出雲市知井宮町628
JR西出雲駅北口から徒歩10分
1 2 3
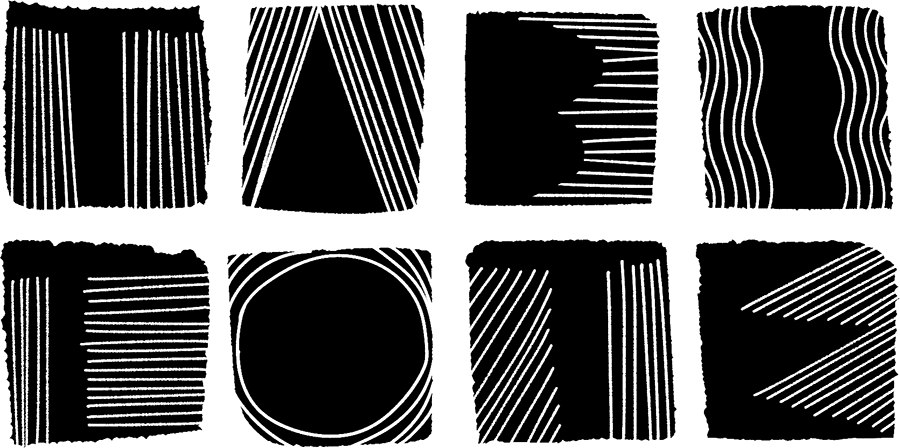





















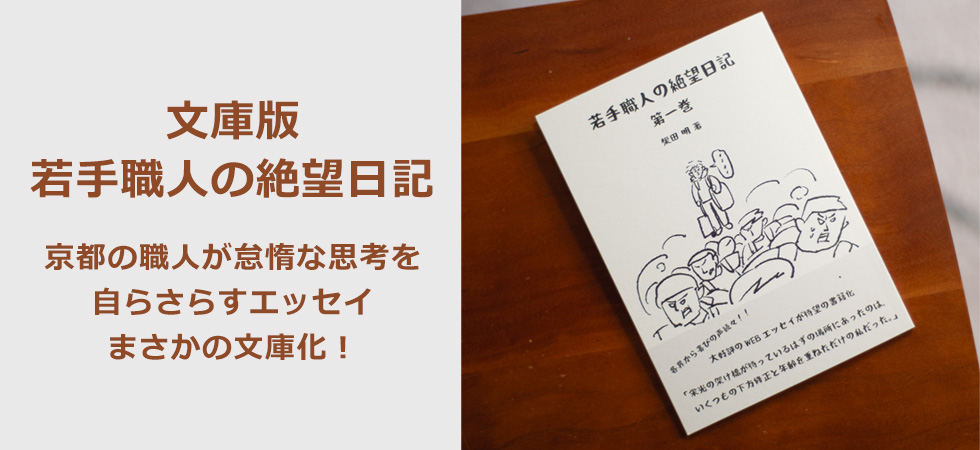
COMMENTS